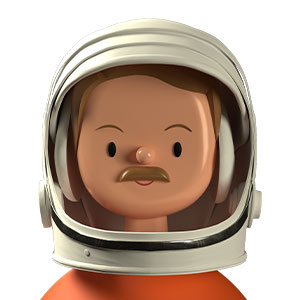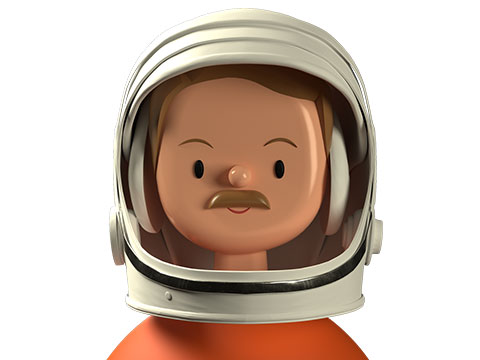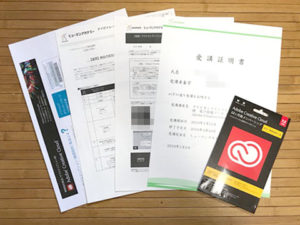ロイヤリティフリーの映像・音楽素材を扱うストックサービスは国内外に多数あります。
ただし、サービスによって素材の利用規約が異なっていることが多く 注意が必要です。
普段 私がよく利用しているMotionElementsで音楽ファイルを選ぶ際に、私が気を付けているのは 以下の4点です。
- ライセンスが「ロイヤリティフリー」の素材を選ぶ
- ロイヤリティフリーの禁止事項を把握しておく
- Youtube安心の楽曲に限定した方がベター
- 楽曲データの編集・加工範囲を確認しておく
この記事では、自分用の備忘録として各項目についての簡単な説明を加えていこうと思いますが、最初におすすめの検索方法を紹介しておきます。

- 定額制プラン素材:チェックいれる ※定額制プランの場合
- Youtube安心のみ:チェック入れる
- ロイヤリティフリー:チェック入れる
- JASRAC登録有り:チェック外す ※
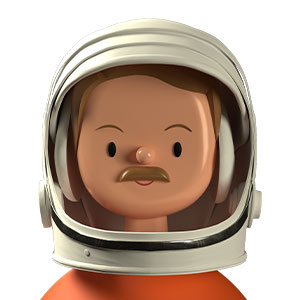
MotionElements 利用規約
ロイヤリティフリー素材使用許諾契約書(シングルシート)
ロイヤリティフリー素材使用許諾契約書 (マルチシート)
記事の目次
ライセンスが「ロイヤリティフリー」の素材を選ぶ
MotionElementsに登録されている楽曲には、大きく以下の3つのライセンスがあります。
- ロイヤリティフリー
- エディトリアル使用限定(エディトリアル使用のみ)
- JASRAC
このうち 商用利用を含む 一般的な動画制作用途であれば、「ロイヤリティフリー」ライセンスのものから選ぶのが基本です。
検索時に「ロイヤリティフリー」にチェックを入れると、「ロイヤリティフリー」ライセンスの楽曲だけを抽出することができます。

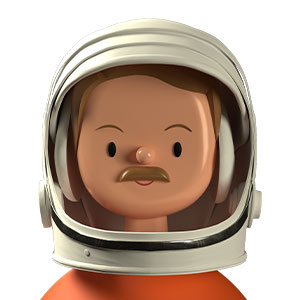
ロイヤリティフリー

一度購入したら、追加のライセンス料が不要で、永久に利用可能なもの。もちろん商用利用も可能(ロイヤリティフリー楽曲の事例)。
Motion Elementsで扱われている素材の大半がこのライセンス。特に理由がなければこのライセンスのもの(だけ)を使用する。
ただし、後述するように「ロイヤリティフリー」ライセンスの素材であっても、禁止されている使い方があるので、規約などに目を通しておく必要があります(ロイヤリティーフリーとは何ですか?:MotionElements公式)。
エディトリアル使用限定(エディトリアル使用のみ)

「エディトリアル使用限定」ライセンスは、学術・教育・ドキュメンタリー系のコンテンツのみで使用が許可されるものです(エディトリアル使用のみとはどういうことですか?:MotionElements公式)。商用利用はできません。
JASRAC

楽曲を使用する際、JASRACへの報告(キューシート)が必要になるコンテンツです(JASRACトラックとは何ですか?:MotionElements公式)。
MotionElementsに支払う購入金額に JASRAC側への使用料も含まれるかたちになっているので、一度購入してしまえば 追加料金などは発生しません。ただし、楽曲使用の度にJASRACへの報告(キューシート)が義務付けられているので、取り扱いが面倒です。
「ロイヤリティフリー」素材の禁止事項を把握しておく
「ロイヤリティフリー」ライセンスの素材は、柔軟な使い方が可能ですが、以下のような使い方は禁止されています。
- ロゴ・商標・サービスマークへの使用は不可
- ポルノ、違法な目的、物議を醸す方法での使用は不可
- 入手した素材を、そのままの形で 転売、再配布することは不可
- 入手した素材を、自分が作成したものだと記載・表現することは不可
- (音楽素材の場合)入手した素材をベースに二次的作品を作成し、それを自分のものとして譲渡することは不可 ※ただし「「音楽制作用途可能」ラベルがあるものに関しては可能
「Youtube安心」の楽曲に限定した方がベター

Youtubeで動画を公開する予定がある場合は、楽曲の検索時に「Youtube安心」にチェックをいれておくことをおすすめします。
これは、YouTubeのContent ID(以下 コンテンツID)に登録された楽曲を検索対象から外してくれるフィルターです。
Youtubeには、楽曲の不正利用を防ぐ目的から、事前登録された曲を含む動画がアップロードされた場合、これを自動検知する仕組み「Content ID」が用意されています(Content ID の仕組み:Youtube公式)。
事前登録された楽曲を含んだ動画をアップロードすると、Youtube管理画面に「第三者のコンテンツと一致しました」といった警告通知が表示されるようになります(YouTubeコンテンツIDとは何ですか?:MotionElements公式)。
MotionElementsには、このコンテンツID登録楽曲も多数 公開されています。※YouTubeコンテンツID登録済みの事例

コンテンツID登録楽曲をYoutubeで使用する場合、MotionElementsで楽曲を購入した正規ユーザーであることを申請すれば、Youtube側の警告通知を解除することができます(申請方法はコチラ)。
以上のように、コンテンツID登録の楽曲でも、申請さえ行えば 警告通知は解除可能です。
ただ、自分で運営するYoutubeチャンネルならともかく、企業のCM・VP動画の制作を請け負っている場合、別途 クライアントに解除方法の説明が必要になってくるため、扱いが面倒です。
このため、私は基本的に「Youtube安心」の楽曲からのみ選曲するようにしています。
楽曲データの編集・加工範囲を確認しておく

ロイヤリティフリー楽曲を配布しているサービスは たくさんありますが、データに対する編集・加工の許容範囲はサービスによって 大きく異なります。
MotionElementsでは、楽曲データの編集・加工について やや厳しめの内容になっています。
音楽制作用途: オーディオコンテンツは、「音楽制作用途」の表記がない限り、以下のことは認められません。
1.作品の全部または一部を同じ作者の別の作品と組み合わせて派生的な作品として使用すること
2.作品の全部または一部を自分の新しい音楽作品の一部として利用すること(例えば、別々の音楽オーディオコンテンツを組み合わせると、出来上がった曲に著作権の問題が生じる)
3.オーディオビジュアルワーク、インターネットのページ、コンピューターやモバイルデバイスアプリケーションの一部として使用すること以外に、作品の全部または一部を変更しただけの成果物を自身の著作物であると主張すること。
4. (i) フェードイン/フェードアウトポイントの設定、音楽の始めと終わりの位置の変更や、使用したい部分の選択などの基本的な編集の限界を越えて編集、変更、加工を加えること。あるいは (ii)ハーモニック・ストラクチャーや、歌詞、メロディーなど根幹をなす部分の変更について編集、変更、加工を加えること。あるいは(iii) コントリビューターのモラルに関わる、無視できない偏見を持たせるような編集、変更、加工を加えること。
特に 大事なのが4番の部分。
MotionElementsでは、楽曲データに加えられる修正は、使いどころを調整するための「カット操作」や、音量を上げ下げする「フェード操作」など、基本的な事項に限定されています。
楽曲データに、なにがしかのエフェクト・フィルタをかけて、メロディや聞こえ方が変わってしまうような加工は一切禁じられています。
- 楽曲の音量を上げる/下げる
- 楽曲を任意の位置からスタートする(または 任意の位置で停止する)
- 1分尺の楽曲の初めの30秒と、お尻の5秒を繋げて、35秒尺の楽曲として使用する
- 30秒の楽曲を任意のポイントでカットし、メロディーをループさせて 2分尺の楽曲として使用する
- 楽曲データの高音域を強調して 明るめの楽曲に変える
- 楽曲データの再生速度を遅くして音を低くする(または 速度を速めて 高音にする)
楽曲そのものが別の曲に聞こえてしまうような使い方は禁止されていると考えてよいでしょう。「楽曲データはそのまま使ってね」が基本です。
例えば、楽曲をループさせる場合でも、数フレーム程度の尺を何度もリフレインさせるような使い方(DJのスクラッチのような)は、NGになってしまう可能性があるかと思います。
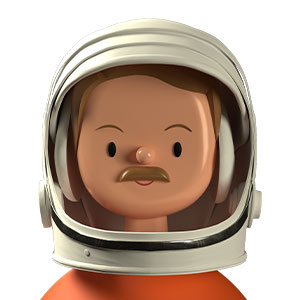
「音楽制作用途可能」楽曲は加工可能だが・・・

一方、MotionElementsの楽曲でも「音楽制作用途可能」とタグのついた楽曲は、編集・加工が可能とされています。
編集・加工が可能な楽曲データの詳細ページには「音楽制作用途使用可能:はい」と記載があります。
ただし、この「音楽制作用途可能」の楽曲を見つけるのは、とんでもなく面倒です・・・というかほぼ無理。
2025.02現在、検索機能に「音楽制作用途可能」楽曲のみを振り分ける設定項目はありません。
方法はただひとつ、各楽曲の詳細ページで「音楽制作用途使用可能:はい」と表記があるものを地道に探していくのみ・・・となっています。