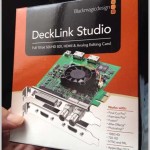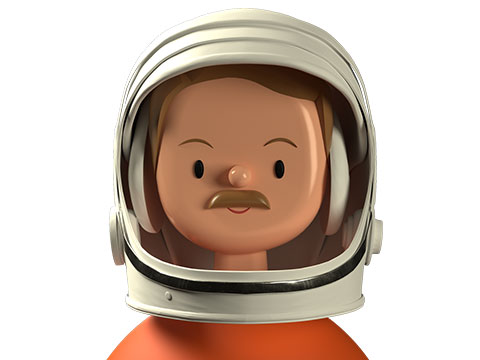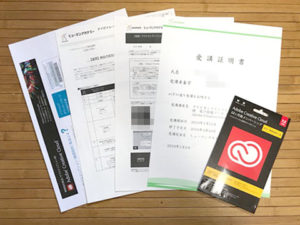こんにちは、高田です。
YouTube用に動画を作成する際に、エンコード設定値に関していつも迷ってしまうので、備忘録としてここにメモしておきます。
記事の目次
覚えておきたい基本事項

まずはYoutubeに動画をアップロードする際に、知っておきたい基本事項を確認しておきましょう(YouTube公式:YouTubeにアップロードする動画におすすめのエンコード設定)。
尺の上限は15分まで(ただし変更可)
YouTubeにアップロードできる動画の長さは、デフォルトでは「最大15分まで」となっています。
ただし、アカウントの確認を完了すると、15分を超える動画をアップロードできるようになります。(公式ページ「15 分を超える動画のアップロード」)
アップロードできるファイルの最大サイズは「ファイル容量:256GB」または「再生時間:12時間」のいずれか小さい方となります。
再エンコードがかかる【重要】
YouTubeでは、アップロードした動画がそのまま表示されているわけではありません。
実は YouTube側で再エンコードしたものが表示されています(参考「YouTubeは推奨設定でアップしても大きくビットレートが削られる(比較検証)」)。
後述するYouTubeの推奨エンコード設定でアップロードした場合でも 再エンコード自体は避けられないようです。
ちなみに ↓こちらのサイトでは 裏技的に4Kサイズにアップコンバートすることで 使用できるビットレートを引き上げる試みが紹介されています。
Youtubeは推奨設定でアップしても大きくビットレートが削られる(比較検証)
Youtube はサーバ側での再エンコードを回避する術がありません。 Youtube が推奨する範囲に収まるデータ量の動画をアップロードしても同じです。 そこで実際にはどれくらいビットレートが削られているのかを検証してみました。
ただし本来x1080サイズしかないものを4Kに拡大した時点で画は荒れるわけで・・・ このへんは後日自分で検証してみたいと思います。
当記事で扱うのは、上述サイトのような裏技的な画質劣化回避方法ではなく、あくまで「YouTubeの推奨する値で動画を書き出す方法」になります。
サポートされているファイル形式
後述の「推奨形式(MP4)」の他にも、いくつかのコンテナに対応しています。
(公式)YouTube でサポートされているファイル形式
YouTube推奨のエンコード設定値
以上を押さえた上でYouTubeが推奨しているエンコード設定を確認しておきましょう。
この推奨値で作成してもYouTube側の再エンコードは回避できません
コンテナ: mp4
・編集リストは含めません(編集リストがあると 映像と音声が同期しないことがある)
・ファイルの先頭にmoovアトムを含める=ファスト スタートにする(設定方法はこちら)
音声コーデック: AAC-LC. Opus. Eclipsa オーディオ
・チャンネル: ステレオ、ステレオ + 5.1、ステレオ + Eclipsa オーディオ
・サンプルレート: 96 khz または 48 khz
動画コーデック: H.264
・プログレッシブ スキャン(インターレースは不可)
・ハイ プロファイル
・2 連続 B フレーム
・クローズド GOP(フレームレートの半分のGOP)
・CABAC
・クロマ サブサンプリング: 4:2:0
・可変ビットレート ※1
※1:ビットレートの上限はありませんが 推奨ビットレートは以下のとおりです。



※「1Mbps = 1000kbps = 1000000bps」
フレーム レート
コンテンツは、記録したときと同じフレームレートでエンコードしてアップロードする必要があります。
インターレース方式のコンテンツは、アップロードする前にインターレースを解除する必要があります。
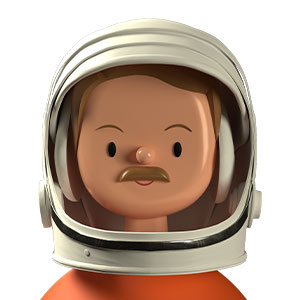
エンコーダの設定方法
EDIUSで書き出す場合
「ファイルへ出力」で「H.264/AVC」を選択して以下のように設定します。
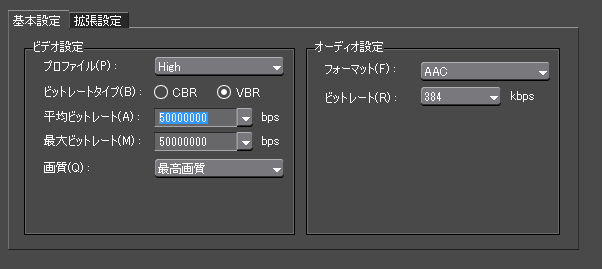
EDIUSの場合「ビットレート」の表記が「bps」を基準にしているので注意。
「1080p」のYoutubeの推奨値は、標準画質「8000kbps」高画質「50000kbps」なので、kbpsをbpsに直すと、それぞれ「8000000kbps」「50000000bps」になります。
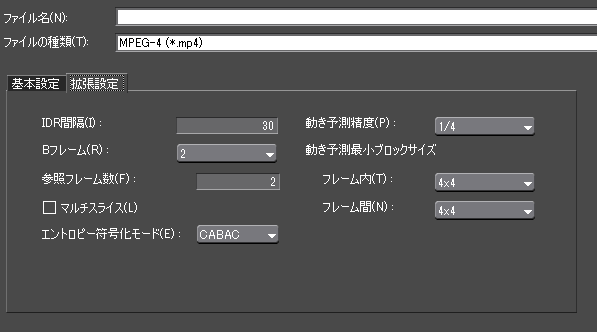
追記:ただし私の環境(Edius ver6)では上記書き出し時にファストスタートの設定ができません。そのため MP4 FastStartなどのツールを用いてmoov atomの位置を変更する必要があります。
詳しくは「WEB動画作成時に”ムーブアトム(moov atom)を先頭に含める”ための具体的な方法」の記事をご覧ください。
まとめ
というわけで YouTube用動画に最適なエンコード値とエンコーダの設定方法でした。
Adobe CreatveCloudの導入/更新を検討している方には「アドビソフト + 動画講座受講セット」![]() がおすすめ。
がおすすめ。
Adobeアプリの動画講座に加えて、CreatveCloud コンプリートプラン(全アプリが利用可能なプラン)が付属し、なんと"学割価格" で利用できてしまいます。
※私が 実際にトレーニング講座を受講した際の感想を記事にしていますので、興味がある方はそちらも合わせて読んでみてください